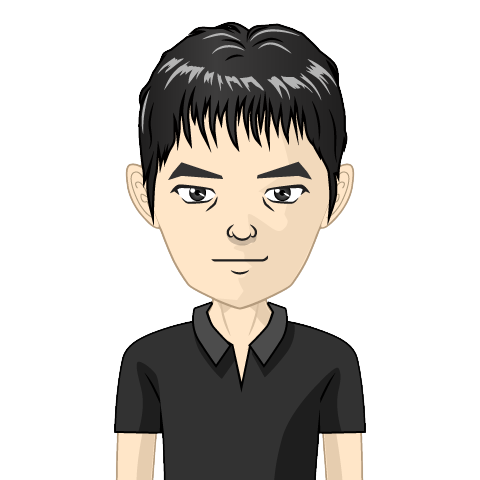#161 Amazon Mechanism イノベーション量産の方程式 要約的感想・学べた&気づけた10のコト
m3-f blogブログです。
今回の要約的感想は、2021年11月発刊、谷敏行著「Amazon Mechanism イノベーション量産の方程式」(日経BP社)を読んでです。
自分の事業や考え方に活かしたいと思えたこともたくさんありました。
・企業としてのアマゾンに興味がある方
・Amazon Mechanismを読んでみようかと思っている方・感想が知りたい方
・事業、ビジネス書に関心がある方
Amazon Mechanism 章構成、、
この本は、ソニー、日本GE、そしてAmazonでの勤務経験とそこでの体験を著者自らまとめられたもので、今のアマゾンの隆盛の背景にあったもの、意外とアナログ&軸になってる概念などがふんだんに書かれています。

章立ては、こんな感じです。
| 序章 | シリアルアントレプレナーとジェフ・ベゾスの共通項と違い |
| 第1章 | 「普通の社員」を「起業家集団」に変えるアマゾンの仕組み・プラクティス |
| 第2章 | 大企業の「落とし穴」を回避するアマゾンの仕組み・プラクティス |
| 第3章 | 経営幹部「Sチーム」の果たす役割 |
| 第4章 | イノベーション創出に関わるベゾスのキーフレーズ |
| 終章 | なぜ今、あらゆる企業と個人にイノベーション創出力が必要なのか |
2005年にAmazonプライム、2007年にアマゾンペイ、2014年にアレクサ、、ほか、様々なイノベーションを次々に起こしてきたAmazon。
さっそく「はじめに」にも、とても大切なことが書かれていました。
Amazon Mechanismを読んで学べた&気づけた10のコト
なによりも「顧客」
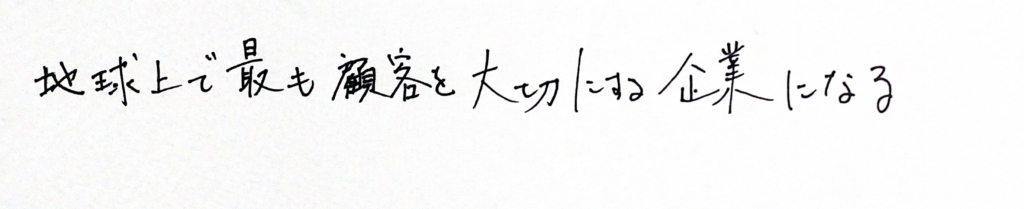
効率化、低価格、、アマゾンの特徴はいくらもあれど、ぶれない軸の一つがこの「顧客志向」だと思いました。
自分の事業でも、根幹をここに置いて取り組みたいなと思います。
一人の天才がことを起こしているわけではない
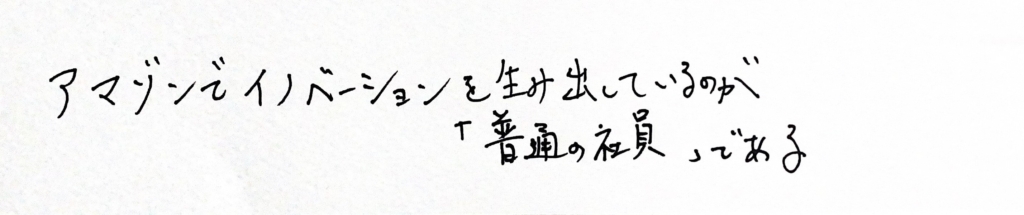
アマゾンと言えば、ジェフ・ベゾス。この一人の巨人が様々なことを生み出しているように錯覚しますが、できている仕組みを活用して、実際にイノベーションを生み出しているのは普通の社員たちでした。
このほか「序章」では、ベンチャー企業に対する考え方として「かつては創業したベンチャー企業を上場(IPO)することをもって成功と考えられていた」が、今ではもはやそうではない、と、時代の変化が書かれていました。

イノベーションアイデア創出のポイント①
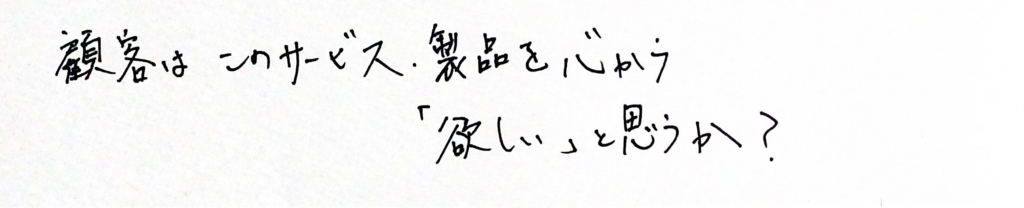
再び「顧客」視点で。
これは第1章に書かれていたことです。「心から欲しい」というのがポイントですね。
小売りの現在位置と、不変なもの
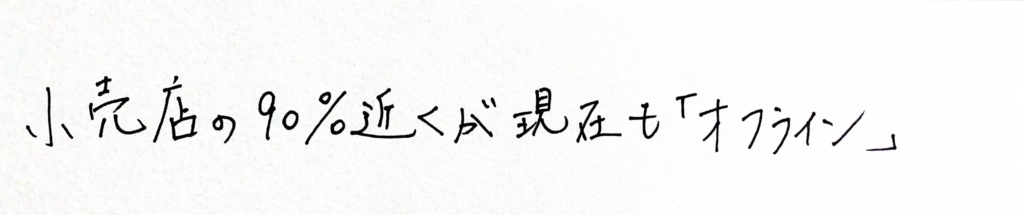
これも第1章から。
オンラインショッピング、ECサイトといろいろありますが、小売り全体で考えるとまだまだこんなもん。
お店に見に行って、商品を見て、買う。そしてレジ待ちという手間を省略したのが「Amazonゴー」の考え方だと、説明されていました。
イノベーションアイデア創出のポイント②
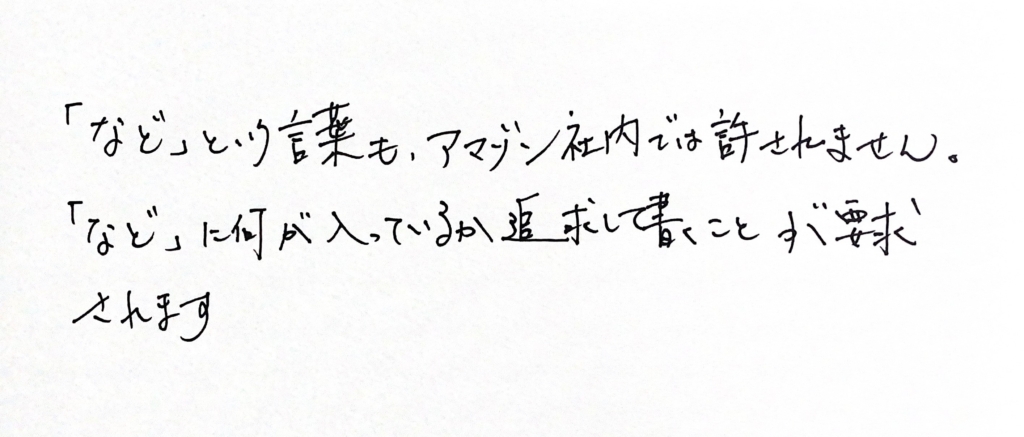
イノベーションアイデアの企画提案の時の社内ルールの一つだそうです。確かに!
どうしても僕も「など」は使ってしまいがちですが、できるだけすべてを具体的に表示するようにします。
イノベーションアイデア創出のポイント②
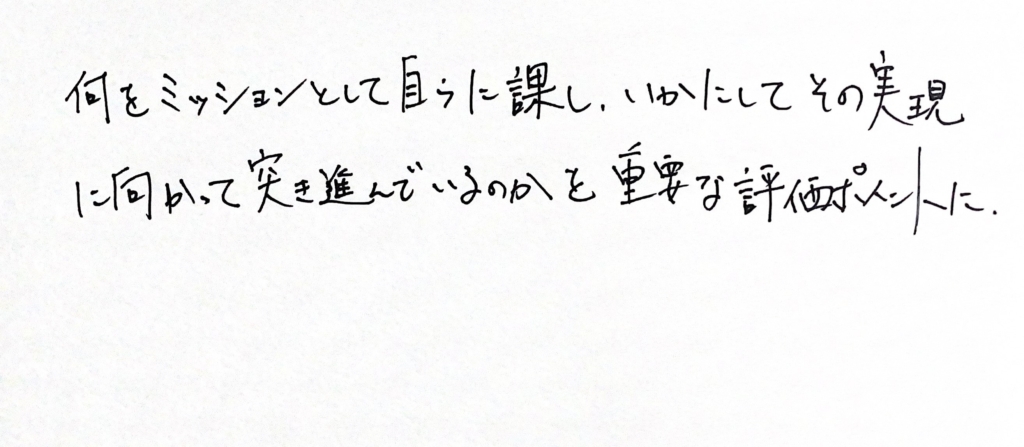
6つ目はこれです。イノベーションアイデアの、評価ポイントとして。
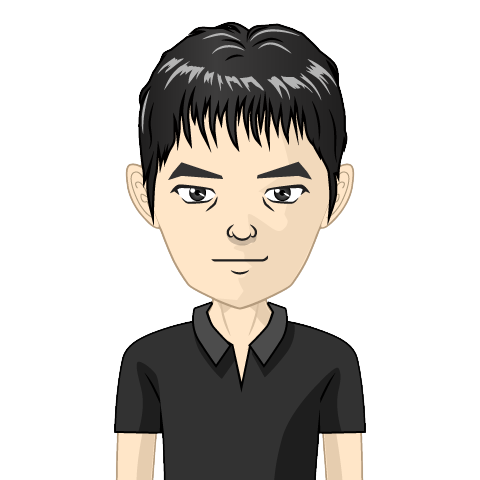
これは、自分に置き換えても、どのタイミングが自身からエネルギーが最大限排出されてるか、と考えてみた時に「実現に向かって突き進んでいるとき」だと思うので、とても納得の話しでした。
第1章ではほかにも、「それはワンウェイ・ドアか、それともツーウェイ・ドアか」という面白い話もありました。
「発明マシーン」
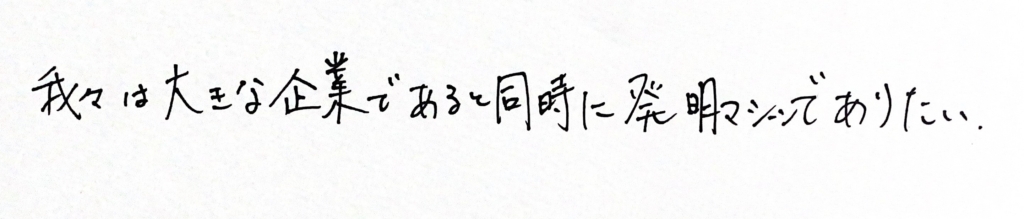
これは第4章にあった話で、前述の「顧客」の視点と共にアマゾンの軸の一つがこの「発明」ということなのかなと感じました。
実態を作る
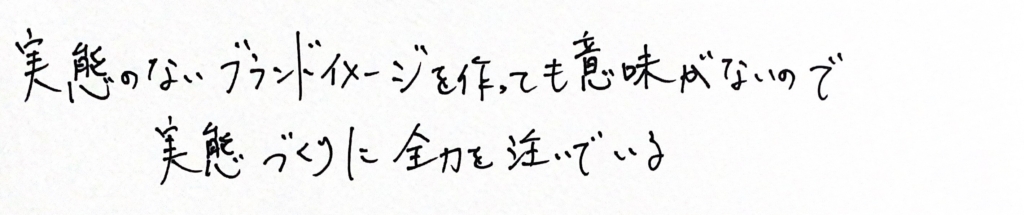
8つ目はこれです。具体的に何をするか、作品として何を残すか、僕の取り組む活動にもとても当てはまる内容の話しでした。

キンドルの役割
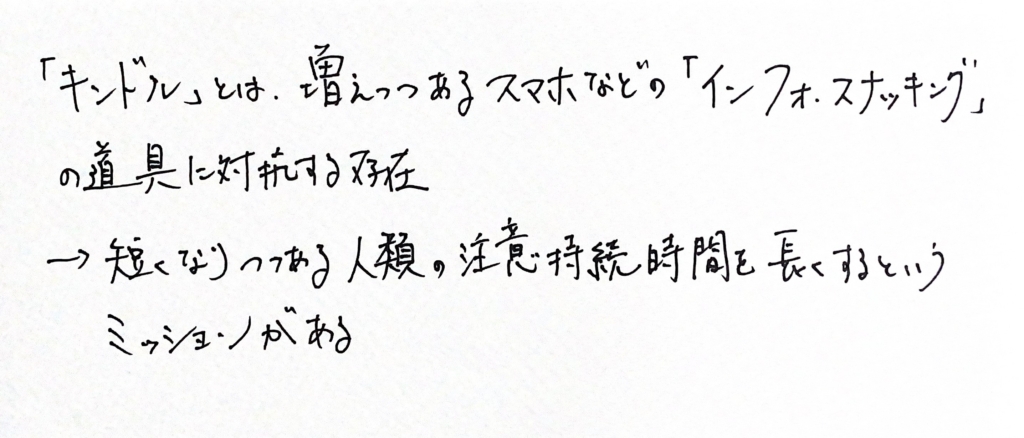
そして9つ目がこれです。「注意持続時間」という考え方。学べてよかったです。
日本企業の得意技
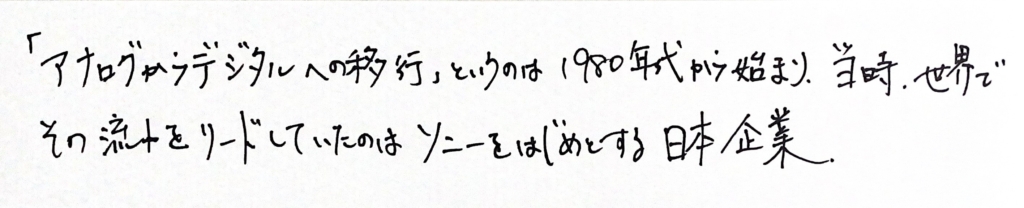
最後、10個目は、終章にありました。
この本で繰り返し述べられてきた「顧客志向」「発明」。ものづくりを得意とするのは我々日本人の強みだと思うので、うまーく「イノベーション」に取り組みつつ、いい仕事をしていきたいですね。
第3章で書かれていた2種類のイノベーション
・持続的イノベーション:既存の製品・サービスの延長線上にあるイノベーション
・破壊的イノベーション:既存の製品・サービスとは別次元の発想から生まれる
Amazon Mechanismの感想記事まとめ~合わせて読みたい記事
今回は、谷敏行著「Amazon Mechanism イノベーション量産の方程式」(日経BP社)の要約的感想でした。
自事業に当てはまる、自分の活動・行動に参考になる情報が満載でした。
終章(なぜ今、あらゆる企業と個人にイノベーション創出力が必要なのか)には、現在来ている5つの波が書かれていました。この分野にはチャンスあり!ってことなんでしょう。
2010年頃から5つのイノベーション・プラットフォームの波が同時に来ている
・エネルギー貯蔵
・人工知能
・ロボティクス
・ゲノム解析
・ブロックチェーン技術