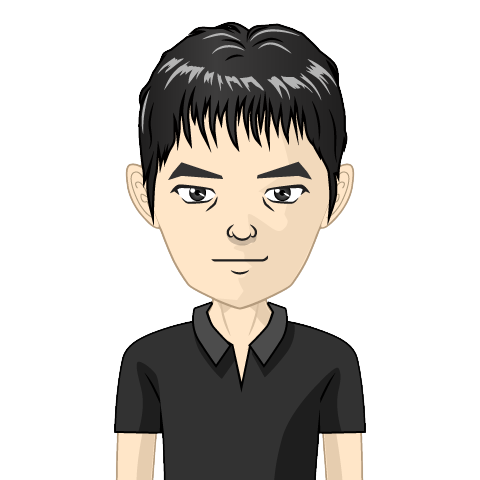#072 おすすめ食生活改善・糖質制限・ダイエット本【医者が教える食事術 実践バイブル2】要約的感想
m3-f blogブログです。
今回は、「医者が教える 食事術 実践バイブル2 20万人を診てわかった医学的に正しい食べ方70」(牧田善二著、ダイヤモンド社刊)の要約的感想です。
この本は、僕が体調不良に苦しんでいた2019年夏に出会った最初の食生活改善のための書籍で、70のバイブルのうち何点かを今も実践し続けて、健康に向き合っています。
・食事制限によるダイエットを検討中の方
・糖質を制限して食生活を改善したい方
・食に対する理解を深めたいと思っている方
当たり前に思っていた食についての一つ一つを再発見できます

食品の70の食べ方、情報が書かれているこの本、これまで何気なく食べていたものの、再発見ができる内容でとても読みごたえがありました。
章立てはこんな感じになっています。
はじめに
序章 「食の正しさ」の正体
第1章 ちまたの「食の都市伝説」
第2章 「三大栄養素」の摂り方
第3章 「食材別」食べ方
第4章 「血糖値」管理法
第5章 「最新医療」との付き合い方
おわりに
長く健康に生きたい!
それはおそらくみなが思うことですね。そのために、食のリテラシー(適切に理解・判断する能力)を身につけよう、というのがこの本のベースにある考え方で、
・太る原因は脂肪の摂りすぎではない
・心筋梗塞や脳卒中を減らすために日本人はもっと肉を食べる必要がある
といったところから、いろんな食品の正しい理解、食べ方が紹介されていきます。
日本人の死因の1位がん、2位心筋梗塞、3位肺炎と続くそれらの病気への予防策の一助ともなる食への理解・食べ方だと読んで感じました。
「糖質」に対する理解を初めて持たされた書籍
それまで(2019年夏まで)なんとなく、「甘いものはよくない~」程度にしか思ってなく、哀しいかな確かに「脂肪が太る」「カロリーを減らさなきゃ」みたいな知識でたくさんものを食べていた30代の自分に、「糖質」の事を気づかせてくれた本です。

糖質(炭水化物)・脂質・たんぱく質を三大栄養素といい、ビタミン・ミネラルを加えて五大栄養素となる。
この中で「糖質」は血糖値を左右する
この血糖値は、「気分(快・不快)」に直接的に関わるもので、気持ちよくなるために「もっと糖質がほしい!」ということになって、気持ちよくなるために最も簡単で効果が高いのが糖質をたくさん使うこと。
結果、繰り返し買わずにいられなくなるという循環を招く
食品メーカーとしては保存料は在庫管理にも便利で、糖質を多量に用いて中毒患者を生み出す
糖質は1日あたり理想的には120g、やせたい人は60gにしたい
という、ちょっと手厳しい表現ですが、このようなことが書かれていてすべてがその通りではないとは思いますが、現実を知りました。
ただ「農耕が行われ米や小麦といった糖質をとるようになった→縄文人の食事に近づけるべき」というのは、前回の記事で書いた「空腹」こそ最強のクスリ にもあった話だったので、やはりそうなのでしょうね。
発見があった&実践しようと思った食べ方などを何点か
この本で70紹介されている食べ方や、間違いやすい認識など、これは!と発見や気づきがあったものを何点か挙げてみます。
・塩分濃度は、薄口しょうゆが18~19%、濃口しょうゆは16%程度
・にんにくのアリシンがビタミンB1の働きを促して疲労回復に良い。ビタミンB1を多く含む豚肉などと一緒に食べてこそ効果が期待できる
・油でベストは「エクストラバージンオリーブオイル」
・魚と鶏肉を交互に、牛肉は月に一度のご馳走にする
・「焼く、揚げる」を避けて、「蒸す、煮る」調理にしよう→老化促進物質であるAGEをあまり増やさない
・シラスを乾燥させた「じゃこ」には、豊富なカルシウムと、そのカルシウムを吸収するために必要なビタミンDが含まれている
・野菜の摂取量は、一日350gが推奨
・野菜の中ではアブラナ科のスルフォラファンという成分が血糖値を下げる
・パセリはビタミンC・E・Kなどを豊富に含む
・チーズはナチュラルチーズを選ぶ
・大豆製品を多く食べる人は乳がんの発症率が低くなる&ダイエット効果がある
・煎った大豆を細かく砕いた「きなこ」はおすすめ
・納豆は脳梗塞などを予防する
・小腹がすいたら、アーモンド・ヘーゼルナッツ・クルミのミックス小袋(30g程度)を食べる
・クロワッサンにはたくさんのバターが使われているため、食パンほど血糖値が上がらない
・グルテンフリーは、実は糖質がたっぷり入っている
・コーヒーに含まれるポリフェノールの一種「クロロゲン酸」に強い抗酸化作用がある
・フライドポテトはスナック菓子と同様にあとを引く食べ物 最初から食べない方が良い

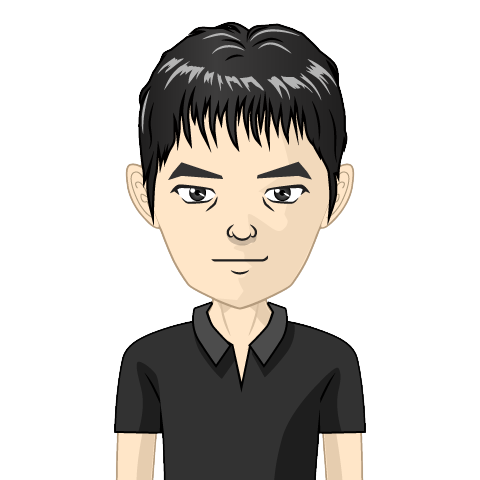
どうでしょうか。これもすべて一概には言えないですが、なるほどと思って、この本を読んでから僕も実践していることが7割くらいあります。
身近な家族に置き換えて、年代別食生活の注意点を3つ
成人である程度年齢が行って来たら、食生活の中で注意すべきポイントを年代別でかんたんに教えてくれる内容の記載もあります。
今の僕と僕の身近な人に置き換えて。
40代→まさに今の自分
BMIが25を超えていたら炭水化物を減らす
炭水化物には中毒性があるので、1日60gまでに制限する
BMI…「Body Mass Index」の略で、カラダの大きさを表す指数ですね。体重(キログラム)を身長(メートル)の二乗で割った値。健康診断の結果の用紙などに記載されています。
40代は今のまさに僕の年代なのですが、過去3年の結果を振り返ってみると
・2019年 24.5
・2020年 20.4
・2021年 21.7(10月検査)
でした。
診断報告書に基準値は、18.5~24.9と書かれていました。
実際に僕の場合は25を超えたことはなかったですが、2019年は一番不調で大変だった時。確かに、当てはまっていますね。
70代→義理のお母さんの年代
女性の多くが「今が一番幸せ」という年代だそうです。
これまで一生懸命働いてきたことへのご褒美の70代だそう。
確かに、お母さん(おばあちゃん)、仕事も落ち着き子離れし、小学生と未就学の孫と毎日本当に楽しそうに生活しているように見えます。
80代以降 僕の父親です
うちの父は、今年88歳。頭はすごく回転していてすごいなと思うのですが、足腰には弱りが出ている。
そして傍らの妻(僕の母)がアルツハイマー型認知症の初期なので、二人暮らしで会話もかみ合わなくなってきてちょっと辛そうです。
80代以降はがんや心臓病よりも、認知症が警戒で、
・積極的に水分補給すること
・イチョウ葉エキス
が良いようです。
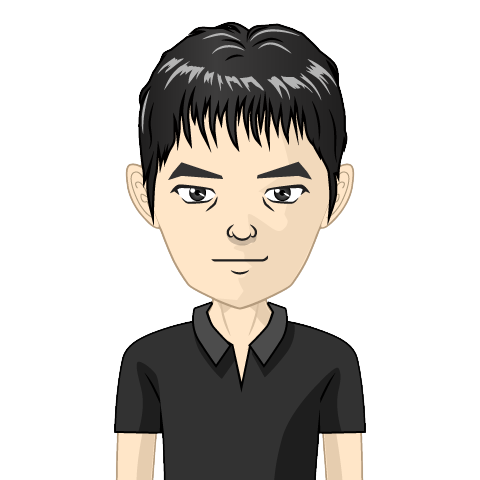
イチョウ葉エキス。
一度探したことがあったのですが、今度実家に戻った時にまた奨めてみようと思います。
「医者が教える食事術2」記事のまとめ

糖尿病専門医で医学博士でもある著者の、少し厳しい表現での指摘もありますが、とても勉強になって実践もしやすいバイブル書。
僕はこの本をきっかけにいわゆる糖質制限をして食生活を改善し、約1年で、体重だけ見ると15㎏のマイナスに成功しました。
極端な無理をしていないので今も継続していて、維持できています。
書かれていることをすべて真似たり実践は難しいと思いますが、悩んだり迷われている方は、部分的にでもチャレンジしてみる価値は大いにあると思います。
次回は、「最強の糖質制限ガイドブック」の要約的感想をまとめてみたいと思います。