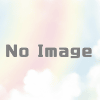🌸 清凉寺(嵯峨釈迦堂)#994
京都検定受験を目指すあなたへ!歴史ある古都の知識を深めるための備忘録として、「嵯峨釈迦堂」として親しまれる清凉寺の重要ポイントを徹底解説します。源融の山荘から始まった創建の歴史、「三国伝来」の国宝釈迦像の背景、そして寺院の変遷まで、合格に欠かせない知識を分かりやすくまとめました。
この記事内容から抜粋した練習問題5問☆
- 清凉寺の前身となった、平安時代初期の歌人・源融(みなもとのとおる)が建てた山荘の名前は何ですか。
- 天慶8年(945年)に夫人の追悼のために釈迦如来像を安置する堂を建立した、醍醐天皇の皇子の名前は何ですか。
- 宋から栴檀(せんだん)製の釈迦如来像を持ち帰った、奈良・東大寺の僧の名前は何ですか。
- 清凉寺の本尊である釈迦如来像が、インド・宋・日本の3国を伝来したという伝承から呼ばれる名称は何ですか。
- 清凉寺は、室町時代の中期以降、浄土宗の寺院として発展しましたが、特に念仏信仰の大道場として栄えた宗派は何ですか。
☆回答は記事の最後にあります。
清凉寺は、京都市右京区嵯峨に位置する浄土宗の寺院で、山号を五台山、本尊は釈迦如来です。古くから「嵯峨釈迦堂」として親しまれています。
🌟 寺院の草創と前身
清凉寺の始まりは、平安時代初期の歌人・源融(みなもとのとおる)がこの地に営んだ山荘「棲霞観(せいかかん)」に遡ります。
- 前身(1)源融の山荘:
- 源融の山荘「棲霞観」が、寛平7年(895年)の源融の死後、寺に改められ「棲霞寺」となりました。
- 前身(2)釈迦堂の建立:
- 天慶8年(945年)には、醍醐天皇の皇子である重明親王(しげあきら)が、亡き夫人を追悼するために新しい堂を建立し、金色等身の釈迦如来像を安置しました。清凉寺は、この棲霞寺に寄寓する(きぐうする=一時的に身を寄せる)形で発足したとされています。

⛩️ 伽藍の整備と「三国伝来の釈迦像」
現在に続く清凉寺の基盤を築いたのは、宋(中国)に渡った東大寺の僧・奝然(ちょうねん)です。
- 奝然による創建計画:
- 奝然は永観5年(987年)に宋から帰国した後、愛宕山を中国の霊場五台山に見立て、その麓の嵯峨に大清涼寺を建立しようと計画しました。
- 本尊の安置:
- 奝然が宋から持ち帰った栴檀(せんだん)製の釈迦如来像を、弟子の盛算(じょうざん)が棲霞寺の釈迦堂に安置しました。これが現在の清凉寺の本尊となっています。
- 信仰の沸騰:
- この本尊は、インド・宋・日本の3国を伝来したという伝承から「三国伝来の釈迦像」と呼ばれ、浄土教の発展とともに信仰が沸騰しました。
🌟 宗派と本尊の特徴(重要文化財・国宝)
- 宗派:
- 当初は天台・真言・念仏の三宗を兼ねた寺として栄え、室町時代の中期以降は融通念仏の大道場としても発展しました。現在は浄土宗に属しています。
- 本尊の特徴:
- 本尊の釈迦如来像は、その独特の形式から「清凉寺方式の釈迦像」とも呼ばれ、国宝に指定されています。
- 像内から発見された絹製の五臓六腑(ごぞうろっぷ)や納入品は、仏像の歴史を知る上で非常に貴重な資料となっています。
- その他の国宝:
- 十六羅漢像(絹本著色)も本尊とともに国宝に指定されています。
📍 周辺情報
清凉寺の西隣には、鎌倉時代の歌人・宇都宮頼綱(うつのみやよりつな)の山荘跡地と伝わる厭離庵(えんりあん)があります。

あわせて読みたい記事
おすすめの書籍
リンク

今回のブログ記事前後の関連記事
前述の練習問題の解答☆
- 棲霞観(せいかかん)
- 重明親王(しげあきら)
- 奝然(ちょうねん)
- 三国伝来の釈迦像
- 融通念仏