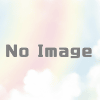⛩️ 京都のお寺 さ行:「じ」から始まる寺院#993
京都検定合格を目指す受験生必見!「さ行」の「じ」から始まる重要な寺院を厳選し、一問一答形式の練習問題付きで徹底解説。在原業平ゆかりの「なりひら寺」から、足利義満が再建に関わった「椿寺」まで、必須知識を効率よくインプットできます。
この記事内容から抜粋した練習問題10問☆
- 床に映る庭の景色「床もみじ」で知られ、摂関家の子弟の入寺により岩倉門跡となった岩倉にある寺院は何でしょうか。
- 文徳天皇の女御(にょうご)である**染殿后(そめどののきさき)**の安産を祈って創建され、**在原業平(ありわらのなりひら)**の晩年の隠棲地として「なりひら寺」の通称を持つ寺院は何でしょうか。
- 蓮台野(れんだいの)に位置し、昔の葬送の地に聖徳太子が建てたといわれる寺院は何でしょうか。
- 軒端(のきば)寺と通称され、角倉了以(すみのくらりょうい)から地の寄進を受けて日蓮宗の日禎(にっしん)が開創し、**時雨亭(しぐれてい)**がある小倉山麓の寺院は何でしょうか。
- 京北町(現・右京区京北)の山中にあり、**光厳天皇(こうごんてんのう)**が庵(いおり)を結んだのが始まりで、**九重桜(ここのえざくら)**が天然記念物となっている寺院は何でしょうか。
- 平安時代の浄土式庭園で有名で、池を挟んで本堂と三重塔が向かい合っている、加茂町(現・木津川市)にある寺院は何でしょうか。
- 国宝の薬師如来立像が安置されている、高雄にある寺院は何でしょうか。
- 上賀茂神社の社務であった松下能久(まつしたよしひさ)が神託により開いた寺院で、**空海(弘法大師)**が刻んだ愛染明王像と自像が安置されている西賀茂の寺院は何でしょうか。
- 全身と光背が白く塗られ**「白不動」**と呼ばれる木造不動明王立像(重要文化財)がある、山城町(現・木津川市)の寺院は何でしょうか。
- **椿寺(つばきでら)の通称を持ち、足利義満の援助で再建され、「五色八重散椿(ごしきやえちりつばき)」や天野屋利兵衛(あまのやりへえ)**の墓がある北区の寺院は何でしょうか。
☆回答は記事の最後にあります。
あなたの備忘録、そして未来の受験生へのエールとなる記事です。
目次
1. 実相院(じっそういん)
- 所在地: 岩倉(京都市左京区)
- 概要:
- 摂関家(せっかんけ)の子弟が入寺したことにより、岩倉門跡となった寺院です。
- 床に映る庭の景色が美しい「床もみじ」「床みどり」が有名です。
2. 十輪寺(じゅうりんじ)
- 通称:なりひら寺
- 宗派:天台宗
- 所在地: 西京区大原野(小塩山)
- 創建: 文徳天皇(もんとくてんのう)の女御(にょうご)、**染殿后(そめどののきさき)**の安産を祈って創建されました。
- ゆかりの人物:
- **在原業平(ありわらのなりひら)**の晩年の隠棲地(いんせいち)として知られ、「なりひら寺」と呼ばれています。
3. 上品蓮台寺(じょうぼんれんだいじ)
- 所在地: 蓮台野(れんだいの)に位置
- 創建: 昔の葬送の地であったこの場所に、聖徳太子が建てたとされています。
4. 常寂光寺(じょうじゃっこうじ)
- 通称:軒端(のきば)寺
- 宗派:日蓮宗
- 所在地: 小倉山の東の麓、二尊院の南に位置
- 開創:
- 豪商の**角倉了以(すみのくらりょうい)・栄可(えいか)**から地の寄進を受け、日蓮宗・本圀寺(ほんこくじ)の第十六世・**日禎(にっしん)**が開創しました。
- 名称の由来:
- 藤原定家(ふじわらのていか)の歌**「軒端(のきば)の松ぞ…」**にちなんで「軒端寺」とも通称されます。
- 寺内の主な施設:
- 妙見堂、歌仙祠(かせんし)、**時雨亭(しぐれてい)**などがあります。
5. 常照皇寺(じょうしょうこうじ)
- 所在地: 京北町(現・右京区京北の山中)
- 宗派: 臨済宗
- 創建: **光厳天皇(こうごんてんのう)**が庵(いおり)を結んだのが始まりです。
- 特徴:
- 桜の名所として知られ、**九重桜(ここのえざくら)**は国の天然記念物です。
6. 浄土寺(じょうどじ)
- 所在地:相国寺(しょうこくじ)のすぐ西にあります。
7. 浄瑠璃寺(じょうるりじ)
- 所在地: 加茂町(現・木津川市)
- 特徴:
- 平安時代の浄土式庭園で有名です。
- 池を挟んで、本堂(九体阿弥陀堂)と三重塔が向かい合って配置されています。
8. 神護寺(じんごじ)
- 所在地: 高雄
- 特徴:
- 国宝の薬師如来立像が安置されています。

9. 神光院(じんこういん)
- 所在地: 西賀茂
- 創建:
- 建保5年(1217年)、上賀茂神社の社務である松下能久(まつしたよしひさ)が神託により開きました。
- 本尊など:
- 空海(弘法大師)がみずから刻んだとされる愛染明王像と自身の像(自像)が安置されています。
- ゆかりの人物:
- 幕末から明治時代にかけての歌人、**太田垣蓮月尼(おおたがきれんげつに)が晩年を過ごした茶所「蓮月庵」**が残されており、蓮月の歌碑もあります。
10. 神童寺(じんどうじ)
- 所在地: 山城町(現・木津川市)
- 本尊など:
- 木造不動明王立像は重要文化財です。
- 全身も光背も白く塗られていることから、白不動と呼ばれています。
11. 地蔵院(じぞういん)
- 通称:椿寺(つばきでら)
- 所在地: 北区の一条西大路
- 創建:
- 神亀3年(726年)に、僧の**行基(ぎょうき)**が創建しました。
- 南北朝末期の市街戦で焼失後、室町幕府三代将軍・足利義満の援助(北山殿の建立余材を寄進)で再建されました。
- 特徴的な椿:
- 本堂前の椿は**「五色八重散椿(ごしきやえちりつばき)」**と呼ばれます。
- 「拾遺都名所図会(しゅういみやこめいしょずえ)」にも「いみじき椿かずかず」と記載されています。
- 墓所:
- 赤穂浪士を援助した天野屋利兵衛(あまのやりへえ)、江戸中期の俳人・**夜半亭(やはんてい)こと早野巴人(はやのはじん)**の墓があります。
12. 直指庵(じきしあん)
- 所在地: 北嵯峨(京都市右京区)
- 歴史:
- 江戸時代、**隠元(いんげん)の法嗣(はっす。法を継ぐ弟子)である独照(どくしょう)が結んだ草庵「没藁庵(もっしょうあん)」**が始まりとされます。
- 名称の由来:
- 「直指人心(じきしにんしん)」の教義を守り、あえて寺名を付けずに「直指庵」と呼ばれてきた経緯があります。
- 特徴:
- 「想い出草」と呼ばれるノートが置かれ、訪問者が心の内を書き残していくことで知られています。

あわせて読みたい記事
おすすめの書籍
リンク

今回のブログ記事前後の関連記事
前述の練習問題の解答☆
- 実相院(じっそういん)
- 十輪寺(じゅうりんじ)
- 上品蓮台寺(じょうぼんれんだいじ)
- 常寂光寺(じょうじゃっこうじ)
- 常照皇寺(じょうしょうこうじ)
- 浄瑠璃寺(じょうるりじ)
- 神護寺(じんごじ)
- 神光院(じんこういん)
- 神童子(じんどうじ)
- 地蔵院(じぞういん)