認知症の薬「ドネペジル」処方後の変化と、両親の薬との向き合い方#826 介護振り返りnote022
京都府立医大付属病院で脳神経の検査を受けた母に、脳の働きを活発にする薬「ドネペジル」が処方されることになりました。かかりつけ医によると、飲み始めは「ふらつき」など足腰に違和感が出ることもあるとのことで、しばらくは心配しながら見守っていました。
幸い、訪問看護師の観察でも特に問題はなさそうで、ひとまず安心しました。
これで母が服用している薬は次の5種類に。
- 消化を抑える「カモスタットメシル」
- コレステロールを下げる「アトルバスタチン」
- 血圧を下げる「ペルジビン」
- 寝つきを良くする「ブロチゾラム」
- そして今回加わった「ドネペジル」
朝食後と夕食後で服用タイミングが分かれるため、訪問看護師さんが1日分を2回に分けて、小袋にしリビングのカレンダーに貼ってくれていました。
それでも、母自身が「今日は何日か」がわからなくなることもあり、「飲んだかどうかわからない」ということがたびたび起こります。
さらにややこしいのは、おそらく20年近く前に言われたであろう、
「血圧が高いときだけ飲めばいい」
という言葉が母の記憶に残っていて、今では毎朝飲むべき血圧の薬を「今日は高くないから」と言って飲まない日が出てきてしまっていました。
ある日、寝つきを良くする薬を朝と夜の2回飲んでしまったのか、訪問看護の際に僕が立ち会ったとき、母がひどく眠そうでボーっとしていたことがありました。
「もし毎日ちゃんと薬を管理できていたら、母の様子も少し違っていたのかな」
そんな思いがふとよぎることもあります。
母にとって「寝つきの薬」はとても大切な存在だったようで、お守りのように感じていた節もありました。
部屋を片付けていたときに、エスエス製薬の「ドリエル」が箱ごと何個も出てきたのはその証拠かもしれません。処方薬が少なくなると、市販薬を買いに薬局へ行っていたこともあったようです。
そんな母に対して、父の方もまた薬との向き合い方が独特でした。
父は、尿酸値を抑える薬、コレステロールを下げる薬、甲状腺ホルモンの補充薬、心臓の血流を改善する薬などを処方されていましたが、自分の体調に合わせて「今日は調子がいいから飲まない」「今日は飲む」という自己判断で服用していたようです。
結果として、処方された薬が1ヶ月で消費しきれないという状況になっていました。
そして父は、「もう10年も同じ薬やで。医者もええ加減なもんで」
と、まるで薬に対する信頼を軽く笑うような言葉を口にしていました。
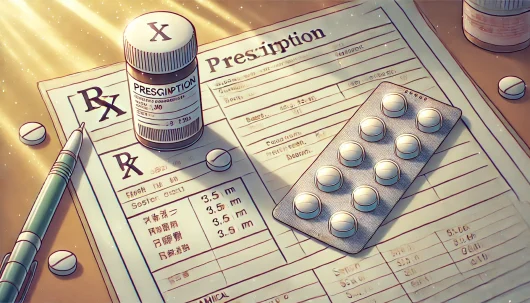
あわせて読みたい記事
おすすめの書籍

今回のブログ記事前後の関連記事


